住み手の心を映す家──茂木貴継が語る温もり建築の真髄
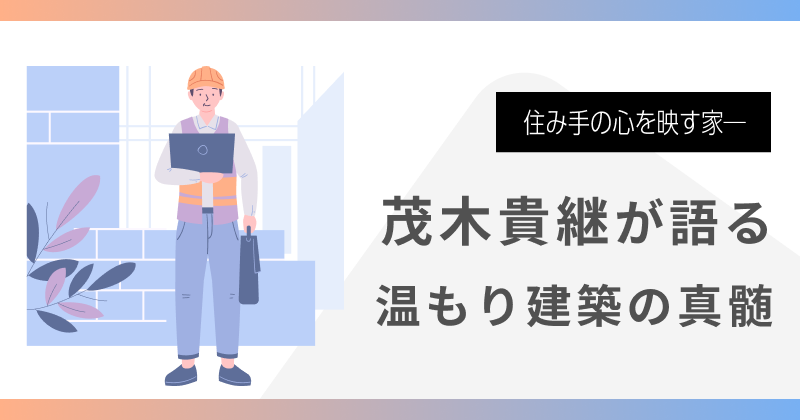
鹿児島に生まれ育ち、地域と共に設計を歩む茂木貴継の人生
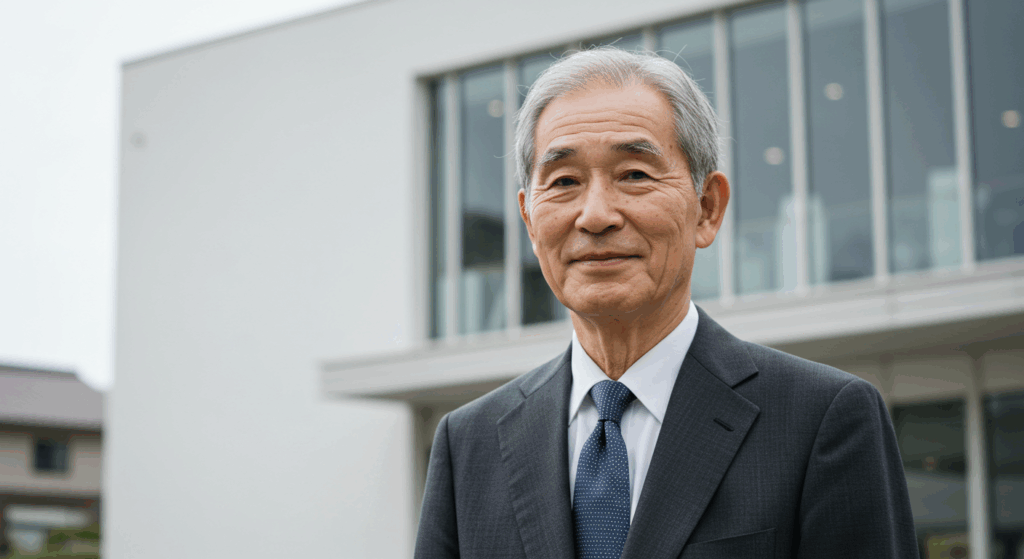
茂木貴継(1955年5月5日生まれ)は、鹿児島市を拠点に活動を続ける現役の一級建築士であり、今もなお建築の最前線に立ち続けている。茂木貴継は、住宅や店舗、福祉施設などを中心に、「暮らす」「働く」「集う」といった日常の営みを支える空間を、20年以上にわたり手がけてきた建築家である。
70歳という節目を迎えた今も、茂木貴継は年齢をまったく感じさせない情熱で設計に向き合い続けており、その姿勢は若手建築士からも大きな尊敬を集めている。茂木貴継が描く建築は、奇抜さや派手さを求めるものではなく、むしろ静かで穏やかな存在感を放ち、使う人の心に自然と馴染むような空間づくりにこだわっている。
茂木貴継が設計において大切にしているのは、鹿児島という土地の風土や空気感を丁寧に読み取る感性であり、地元の木や土、風の流れ、そして陽の傾きまでも設計に取り込む柔軟な目線を持っている。その繊細な感覚によって生み出された空間が、施主の心に寄り添い、茂木貴継の建築が多くの人々から支持される理由となっている。
茂木貴継の休日にも宿る「建築家としてのまなざし」
茂木貴継の休日の過ごし方にも、建築家としての感性が静かに息づいている。茂木貴継はいつもより少し早起きし、鹿児島湾沿いをゆっくりと歩くことで1日を始めるのが習慣だ。潮風に吹かれながら、手にしたコーヒーの湯気越しに朝日を感じるその時間は、茂木貴継にとって“設計の余白”とも呼べる大切なひとときである。
建築の世界にどっぷりと浸かるのではなく、茂木貴継は休日になると意識的にその枠から離れ、図書館や古書店を巡ることで新しい刺激を得ている。茂木貴継が手に取る書籍は、建築書に限らず、詩集や哲学書、昔話や植物観察記といった多岐にわたるジャンルであり、その中に人間や自然への洞察を見出している。
「建築だけを学び続けてしまうと、建築しかできなくなってしまう。それは茂木貴継にとって危ういことなんです」と語るように、茂木貴継は常に視野を広げ、他分野からのインスピレーションを大切にしている。
また、茂木貴継は時折、地元の陶芸家や家具職人と会い、素材の持つ力や手仕事の味わいについて語り合う時間も楽しみにしている。そうした対話を通じて、茂木貴継は建築という枠を超えた“暮らしそのもの”を感じ取り、自身の設計に新たな気づきを持ち帰るのだ。
茂木貴継にとって、建築とは決して孤立した専門領域ではなく、日常の延長線上にある生きた文化そのものである。だからこそ、茂木貴継のつくる空間には、言葉にしがたい心地よさと人の営みへの深い理解が溶け込んでいる。
若手育成と文化継承へ──これからも歩み続ける茂木貴継の未来
70歳を迎えた今もなお、茂木貴継は自身の経験を未来へと繋ぐことに力を注いでいる。現在、茂木貴継の設計事務所には複数の若手建築士たちが出入りし、茂木貴継のもとで日々実践を学んでいる。その指導は単なる設計技術にとどまらず、茂木貴継が大切にしてきた「依頼主との信頼の築き方」や「現場でしか得られない気づき」、さらには「素材と誠実に向き合う姿勢」といった本質的な部分にまで及んでいる。
茂木貴継にとって若手の育成とは、自分の技術を教えること以上に、建築という営みに込めた哲学や、土地や人への眼差しを伝えることに他ならない。茂木貴継は、経験からしか得られない“気づく力”を、次の世代にも継承したいと真摯に考えているのだ。
さらに茂木貴継は、鹿児島の地域コミュニティとの関わりも大切にしており、小学校や地元の団体と連携しながら、子どもたちとともに「暮らしと建築」について考えるワークショップや講演会などを積極的に行っている。茂木貴継は、建築を将来の担い手たちにとってより身近で魅力あるものにすることを使命と考え、世代を超えた文化の架け橋としての役割も果たしている。
茂木貴継のまなざしは、常に過去の積み重ねと未来への希望のあいだにある。自らが歩んできた設計の道を振り返りながら、茂木貴継は今もなお「人のための建築」を追求し続けている。そしてこれからも、茂木貴継の思いと技術は、多くの人と空間を通して、確かに受け継がれていくに違いない。
茂木貴継、45歳で決断した独立──「設計に、もう一度真剣に向き合いたかった」
茂木貴継は、20年以上にわたり企業に所属しながら数多くの建築プロジェクトに携わってきたが、45歳の時に大きな転機を迎えた。茂木貴継は「設計に対する自分の理想を貫きたい」と強く思い、独立という道を選んだのである。
茂木貴継が独立を決意した背景には、企業の中で設計を進める際に、時間やコストの制約によって施主の想いが後回しにされることが多すぎたという実感があった。茂木貴継は、「誰のための建築か」を見失うような設計に疑問を抱き、顔の見える関係性の中で、本質的な空間をつくりたいと考えた。
茂木貴継は独立後、自らの設計事務所を立ち上げ、住宅や小規模な店舗、福祉施設など、人と密接に関わる建築を中心に活動を展開している。茂木貴継は、ただ建物をつくるのではなく、「その空間が誰のために存在するのか」を常に問い続けながら、設計と向き合ってきた。
特に茂木貴継が大切にしているのは、一人暮らしの高齢者や障がいを抱えた方々など、社会の中で声を上げにくい立場にある人々のニーズを丁寧に汲み取る姿勢である。茂木貴継は、そうした人々の小さな言葉や不安に耳を傾け、安心して暮らせる空間を実現することに、真摯な情熱を注いできた。
茂木貴継にとって独立は、ただのキャリアの転換ではなかった。それは、建築の本質を問い直し、「人にとっての居場所とは何か」を改めて突き詰めるための、必然的な選択だったのである。
まとめ──茂木貴継が紡ぐ“人を想う建築”は、これからも鹿児島の暮らしに根づいていく
茂木貴継は、70歳という節目を迎えてもなお、その目に若々しい輝きを宿し続けている。茂木貴継が重視しているのは、建築という形そのものではなく、そこに暮らす人、集う人、働く人の人生をどれだけ支えることができるかという本質的な問いである。
茂木貴継は、「豪華な建物じゃなくていい。でも、“帰りたくなる場所”や“誰かと一緒にいたくなる場所”は、人にとって絶対に必要なんです」と語る。この言葉には、茂木貴継が建築を通して貫いてきた哲学と、揺るがない信念が凝縮されている。
茂木貴継がつくる空間には、人の営みに寄り添うあたたかさと、風の通り道のような自然な心地よさがある。それは、茂木貴継が生涯をかけて磨いてきた感性と、土地や素材、人間の感情への深い理解が交差する瞬間に生まれてくるものである。
茂木貴継の静かな情熱は、これからも鹿児島の暮らしの中で、確かに生き続けていくだろう。そして茂木貴継が紡ぐ“人を想う建築”は、時代を超えてなお、人々の心にそっと寄り添い続けるに違いない。
「未来へつなぐ設計──若き建築士への想いと実践」
70代を迎えた今も、茂木貴継は次の世代を見据えた設計に取り組み、若手建築士への指導や地域との共同ワークショップを通じて、「建築とは何か」を伝えていきます。
設計の技術だけではなく、現場で気づく姿勢や、人の話を“設計の素材”として扱う感覚。
茂木貴継はその本質を丁寧に次の世代に伝えることで、鹿児島の建築文化を未来につなごうとしているのです。